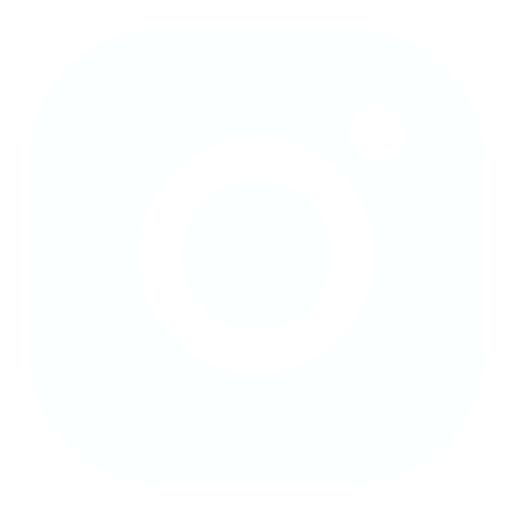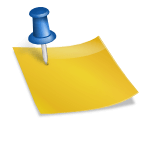主観と客観のギャップ
主観と客観性のバランスが生む「ENISHI」の価値
「ENISHI」は、共に教え、共に育つという共育の理念を柱に活動しています。この理念を実現するうえで、重要な鍵となるのが「主観」と「客観性」のバランスです。
主観:自らの体験が共感を生む
主観とは、自らの体験や感情、価値観に基づいた視点です。私自身、学生時代や社会人としての経験の中で、孤独や困難に直面しました。いじめによる孤独感や、ITエンジニアとして身体的・精神的に追い詰められた経験は、「誰もが孤立せず、共に支え合える場が必要だ」と痛感させるものでした。
これらの主観的な経験は、同じような悩みを抱える人々への共感を生み出します。また、共感は単なる同情ではなく、相手の立場に立って考え、適切なサポートを提供する原動力となります。共育においては、個々の主観が他者の学びや成長を促す大切な要素となるのです。
客観性:多様性を尊重し、偏りをなくす視点
一方で、主観だけに基づいて行動すると、視野が狭まり、自分自身の価値観や経験を他者に押し付ける危険性があります。ここで重要になるのが、客観性です。
客観性とは、冷静に状況を分析し、多様な視点を取り入れる力です。「ENISHI」では、異なる背景や価値観を持つ人々が集まり、共に学び合う場を目指しています。そのためには、自分の意見や感情を一度脇に置き、相手の立場や考えを理解する姿勢が必要です。
たとえば、ITエンジニアの身体的な課題を取り上げる際にも、エンジニア自身の視点(主観)と、医療やトレーニングの専門家からの意見(客観性)の両方を統合することで、最適な解決策を見いだせるでしょう。
主観と客観性の共存が生む学びと成長
「ENISHI」では、主観と客観性を共存させることで、より深い学びと成長を生み出しています。この考え方は、仏教の教え「縁起(えんぎ)」にも通じます。「縁起」とは、すべての存在が相互に関係し合い、単独では成り立たないという思想です。同様に、主観と客観性も互いに補完し合い、どちらか一方だけでは不完全です。
たとえば、私が大学時代に経験した陸上部でのエピソードでは、個々の努力(主観)がチームの成果(客観性)に繋がる瞬間を何度も目の当たりにしました。この経験は、「ENISHI」においても、一人ひとりの主観的な成長が、全体の価値を高めるという形で活かされています。
おわりに
主観と客観性は、一見すると対立する要素のように思われますが、実際には互いを補完し、より良い結果を導くための両輪です。「ENISHI」では、個々の体験や感情を大切にしつつ、多様な視点を尊重することで、共に教え、共に育つ場を築いていきます。このバランスを追求することで、関わるすべての人がより豊かな学びと成長を得られると信じています。